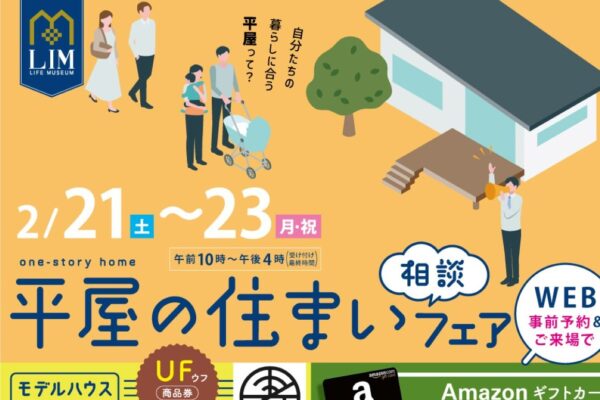「男性の育休」って本当に必要?パパとママ2人で親になるために知っておいてほしいこと|「ゆるりとHappy子育て」⑧助産師・森木由美子さんが子育てを楽しめる知識、技術を紹介します

「子育てを楽しみたいけれど、うまくいかない」「かわいいはずのわが子が、かわいく思えない」。そんな思いを抱えていませんか?
コラム「ゆるりとHappy子育て」では助産師の森木由美子さんが「これを知っておくと子育てがもっと楽しめる」という知識や技術を紹介していきます。
この数年で当たり前になってきた「男性の育休」。一方で、「男性の育休って本当に必要?」という声もまだまだあります。パパとママが 2 人で親になるために必要なこととは?産後ケアに取り組む助産師さんの目線で紹介します。
「ゆるりとHappy子育て」はこちらから
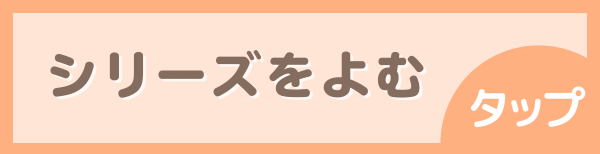
「誰かがいないと育児が回らない状態」になることも…
赤ちゃんが生まれてすぐの時期は、ママと赤ちゃんが一つのリズムを探りながら過ごしていく。そんな時間だと私は感じています。
おっぱいを飲んで、泣いて、眠って――。その繰り返しの中で、赤ちゃんは少しずつこの世界に慣れ、ママは“母親としての自分”を見つけていきます。
この数年で、育休を取得するパパがずいぶんと増えました。
男性の育休は間違いなく必要な制度です。
核家族化が進み、地域や家族の支えが得にくくなった今、赤ちゃんとママを支える存在として、パパが家庭にいることの意義はとても大きくなっています。

一方で、「男性の育休って本当に必要?」という声を耳にします。
子育て世代でも感じ方はさまざまで、「夫がいてくれて助かった」という声もあれば、「正直、気を使って疲れた…」という本音もちらほら。
男性の育休は制度として整いつつある一方で、「男性が育児にどう関わればいいのか分からない」「何が正解か分からない」といった戸惑いが、現場ではまだまだ残っているのが現実です。
パパとママがうまくいっているようで、気になるご家庭もあります。
例えば、授乳時間を“シフト制”のようにパパとママで分担するご家庭。授乳アプリをパパが記録し、抱っこ紐も 2 人で交代で装着しています。
一見とても協力的に見えますが、ママが「1 人でできる感覚」を持てないまま、「誰かがいないと育児が回らない状態」になることも。
パパが仕事に戻ったとたん、「赤ちゃんが泣いたら何もできない」とママが戸惑い、家庭全体が不安定になることもあるのです。
「男女平等=パパとママは同じ役割」でしょうか
育児はパパとママが 2 人で取り組むもの。けれど、そこには父と母、それぞれの役割の違いがあります。
よく「男女平等」と言われますが、「平等=全く同じ」ではないと私は思います。
赤ちゃんが最初に出会い、リズムをつくるのはやっぱりママ。特に母乳育児では、授乳の積み重ねがホルモンや感覚を整え、ママとしての自信や育児の軸を育ててくれます。
そこにパパが対等に関わろうとしすぎると、かえって授乳がうまくいかなかったり、ママが「誰かがいないとできない状態」にとどまってしまうことも。

だからこそ、パパには違う形の関わり方が求められます。
授乳後にパパが抱っこを代わって寝かしつけをしたり、家事を引き受けて洗濯をしたり、ご飯を炊いたり。
凝った料理でなくても、おみそ汁とご飯があれば、ママの心に余白が生まれます。
私自身も子どもたちが小さい頃、夫が出張で不在の時に自然と“ワンオペ育児”になる場面が何度もありました。
子どもが泣いていても、ご飯を作り、お風呂に入れ、寝かしつけまで 1 人でこなす日々。
決して楽ではなかったけれど、「 1 人でできるかできないか」ではなく、自分がやるしかない状況の中で、少しずつ「自分でもやっていける」という自信が育っていったように思います。
「育児は大変だけど、豊かだった」と思えるように
出産・育児が大変なのは、当たり前のこと。
「大変だからなんとか楽にしなきゃ」とだけ捉える風潮に、少し違和感があります。
以前、現場でこんな言葉をもらったことがあります。
「育児は大変だけど、豊かだったと、後から思えるように」
その言葉に、私はとても救われました。
今、私たちに必要なのは「育児の大変さを否定しないこと」。大変さの中でこそ、親としての軸や、家族のリズムが育っていくのだと思います。

ちなみに、ドイツでは妊娠期から、2 人で親になるための準備が当たり前にされています。両親学級は保険適用で 14 時間、出産後も最大 36 回まで助産師(ヘバメ)の訪問があり、家族で育児をスタートする支援体制が整っています。
日本にはそこまでの制度はありませんが、「産後ケア」という仕組みがあります。
パパ育休と合わせて産後ケアを活用することで、まずママが体を休め、赤ちゃんとのリズムを整える時間を確保できます。
その後、パパと一緒にお世話を練習したり、家事分担を話し合ったり、「共同の育児練習の場」として活用することもできます。
「パパが育休を取っているので、産後ケアは利用しない」というご家庭があります。でも、実はママが無理をしていたり、パパが「何が正解なのか分からない」と悩んでいたりします。
2 人で育てていくために、上手に活用してほしいなと思います。
育児は完璧じゃなくていい。むしろ、うまく手を抜けることが大事。
育児に“ちょうどいい塩梅”があるとしたら、それはきっと、「 2 人の間で育てるリズム」のことかもしれません。
赤ちゃんが泣いたら抱っこして、笑ったら一緒に笑って、うまくいかない日は「まぁ、いっか」。
パパとママがそんなふうに肩の力を抜いて、「やれることから、ぼちぼちでいこう」と思える子育てが広がるといいなと思っています。
「男性の育休」について高知県が企業向けに開いている「未来のパパママ 共育て講座」を取材しました。森木さんの講演を紹介しています。
「男性の育休」はなぜ必要?夫婦で育休を取るメリットは?職場復帰後に活用できる子育て支援制度とは?|高知県の「未来のパパママ 共育て講座」に参加してみた

この記事の著者
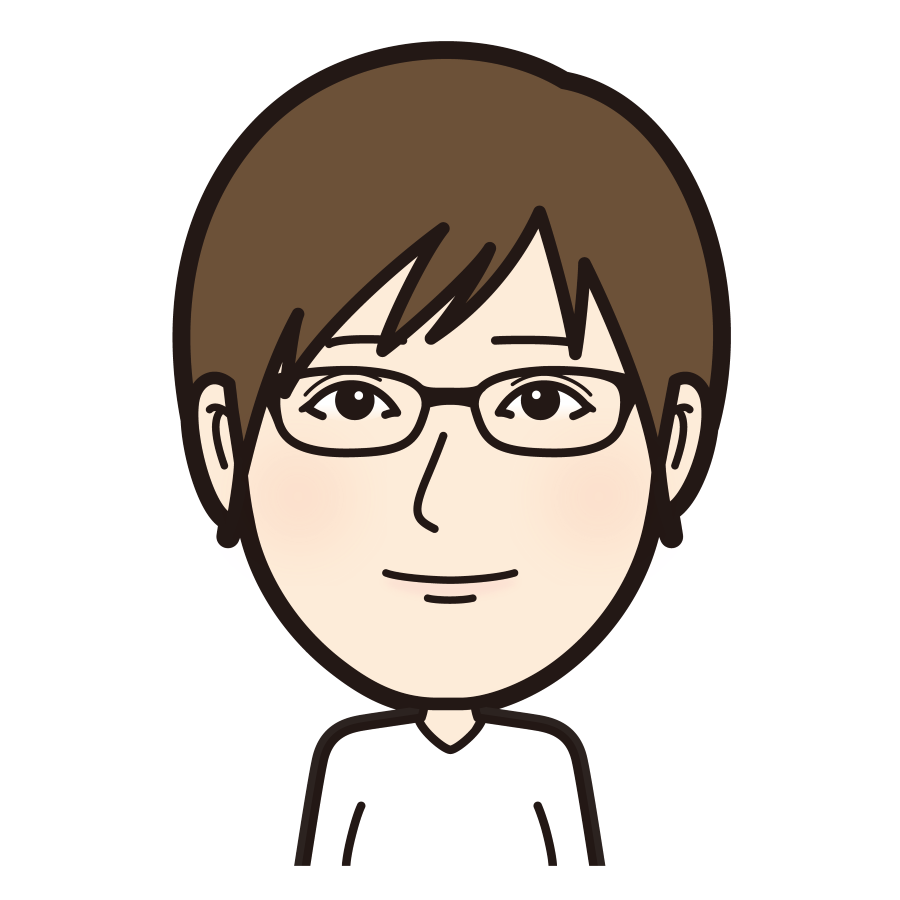
森木由美子
自分自身の出産、子育てを通して、産前産後のケアの重要性を痛感し、2015 年に助産院はぐはぐを開業。出張での産後ケアに取り組んでいます。
2 児の母。趣味はピアノ、クラリネット演奏。
関連するキーワード
関連記事[子育て]
-

「母乳が足りない」「うまく飲んでもらえない」…授乳で悩んでいませんか?|母乳育児を軌道に乗せるこつは「抱き方」と「含ませ方」。助産師・森木由美子さんに聞きました
-
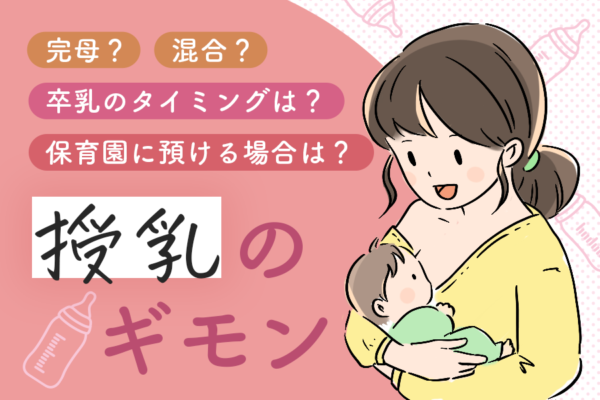
保育園に預ける場合はミルクに切り替えた方がいい?「母乳メインの混合授乳」ってどう進める?卒乳のタイミングは?|授乳の疑問について、助産師・森木由美子さんに聞きました
-

抱っこひもを正しく使い、腰痛を防ぎましょう!|ベルトの位置・締め方、赤ちゃんの態勢…抱っこひも相談会で助産師さんがアドバイスしました
-

赤ちゃんの抱っこ、遊び…ちょっと見直してみませんか?|“不自由”と“体の中心”を意識してみて…助産師・森木由美子さんが「赤ちゃんのトリセツ」で解説しました

 子育て
子育て