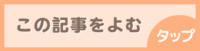思春期の子育て…子どもを安易に理解しようとしていませんか?|親が備えておきたい「ネガティブ・ケイパビリティー」とは?兵庫教育大学の今西一仁さんが語りました

子どもの発達段階を理解して関われていますか?はまゆう教育相談所の研修会から子育てのヒントをお届けします
わが子をきちんと理解し、気持ちに寄り添いたいと思うのが親心。しかし、子どもが成長して思春期を迎える頃には、親と話してくれなくなったり、時には反発されたり。「この子は何を考えているんだ」と戸惑う場面が出てきます。
不登校や子育ての相談に乗る「はまゆう教育相談所」の第 3 回研修会では、思春期の子どもへの向き合い方について、兵庫教育大学非常勤講師の今西一仁さんが語りました。
親子の関わりがうまくいかなかった時は「親が自分の捉え方を見つめ直すチャンス」と今西さん。特に、子どもの心と体が大きく変化する思春期は、子どもを安易に理解しようとしないことが大切です。親が備えておきたい「ネガティブ・ケイパビリティー」について紹介します。
目次
「はまゆう教育相談所」では不登校や子育ての相談に乗っています
「はまゆう教育相談所」は高知市小津町の高知県立塩見記念青少年プラザにあります。小学校の元校長先生らがボランティアで運営していて、無料で相談できます。

活動の一つに「研究」があり、毎年テーマを決めて研修会や教育座談会を企画しています。
2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」で 8 回開かれます。

第 3 回は「思春期の子どもと向き合うということ~「子ども理解」から「関係性の理解へ」~」をテーマに 7 月 5 日に開かれました。
講師の今西一仁さんは元教員で、高知県内の高校で国語を教えてきました。公認心理師や学校心理士スーパーバイザーなどの資格を持ち、現在は兵庫教育大学の非常勤講師や学芸中高の教育相談アドバイザーなどを務めています。
著書に「紙上ゼミナールで学ぶやさしい交流分析」(ほんの森出版)があります。
「過去」と「他者」は変えられない…関係がうまくいかない時は自分の捉え方を見直してみて
今西さんは高校で国語を教えながら、心理学を学び直しました。きっかけはある生徒の存在でした。なにかと突っかかってくるその生徒に苦手意識を抱き、夢に出てくるほどでした。
「生徒から走って逃げて疲れるという夢を 10 回以上見ました。最後の夢ではその生徒がバスに乗っていました。私はそのバスに乗り込んであいさつをして降りた。その後、その生徒の夢は見なくなりました」
心理学では「過去と他者は変えられない」と言われます。イソップ寓話「北風と太陽」で、旅人の外套(がいとう)を脱がせようと強い風を吹かせて失敗した北風のエピソードは「他者は変えられない」を象徴する話です。
「他者を無理に変えようとすると、より抵抗が強まります。それまでは子どもの中で何が起こっているのかを理解しようとしてきましたが、子どもとの関係性の中で自分に起きた気づきに、もっと自覚的になろうと考えるようになりました」
今西さんはこうした経験から「子どもとの関わりがうまくいかなくなった時は、自分の捉え方を見つめ直すチャンス」と考えています。

今西さんは講演などで「『わかる』ことは『分ける』こと」と語ってきました。
「私たちは目の前の事象を自分の経験の枠組みの中に分類できた時に『分かった』と感じて、納得したり安心したりします」
「『わかりやすさ』とは『わかりにくい部分』を捨てることで生まれます。しかし、分かりやすくなればなるほど、物事の一部分しか捉えることができなくなっていくというジレンマがあります」
親はわが子の言動からわが子を理解しますが、もしかしたら一部分しか見えていないのかも…という自覚が大事だそうです。
意図せず始まる第二次性徴…思春期の性は体の問題であり、心の問題です
思春期の始まる時期は諸説あり、また個人差もありますが、だいたい小学 5 年生ごろから。小学 3~4 年生が「前思春期」となります。
前思春期では心理的変化が起こり、それまで当たり前だと思って疑いもしなかったことに違和感を抱きます。自我の体験の一つが「自分が死ぬ」と気づくこと。「私は誰?」という自意識も強まっていきます。
思春期では身体的変化が起こります。体の変化は第二次性徴によって、本人の意図しないところで始まります。特に女の子は初潮年齢が早まり、「子どもでいられる期間」が短くなっているそうです。
「思春期の性は体の問題でもあり、心の問題でもあるので非常に難しい。『どうして胸が膨らむの?』『どうしておちんちんがあるの?』『自分はトランスジェンダーかもしれない』などと混乱してくるのは当たり前。皆さんにも混乱があったんですが、忘れているだけなんですね」

思春期では友人との関係も発達していきます。特定の友人と親密になり、大人に対して秘密を持つようにもなります。
ちなみに、うそをつくのも秘密を持つのも、正常な発達だそう。
「うそは 4 歳ごろからつきます。『自分とお母さんは別の人』と理解できるようになったからうそをつくんですが、幼児はまだ秘密は持てません。秘密には自我が必要なんです」
思春期の子どもは親に対し、「自立」と「依存」という相反する感情を抱きます。親からの自立を求める中で、友人関係がより重要になっていきます。
自己認識の変化、葛藤、感情の不安定さ…「思春期心性」は大人にもあります
思春期をめぐる友人関係、仲間関係には近年、変化が起きています。
小学校中学年の「ギャング・グループ」が希薄化し、小学校高学年から中学生の「チャム・グループ」が肥大化。高校生以降の「ピア・グループ」の形成が遅くなっているそうです。
ギャング・グループ
行動をともにする遊び仲間のこと。小学校中学年の男子に多い。秘密基地を作ったり、ナイフを使ったり、親や教師の課すルールを破る。外面的な同一行動による一体感を重視している。
チャム・グループ
チャムは「親友」。好きな芸能人など同じ興味、関心で結ばれる仲良しグループで、小学校高学年から中学生の女子に多い。内面的な類似性、同質性の確認による一体感を重視している。同調圧力が強い。
ピア・グループ
ピアは「仲間」。お互いの違いを認め、価値観や理想、生き方などを語り合う。同調圧力はなく、集団への出入りも自由。

「チャム・グループ」は女の子に特徴的に見られるグループですが、最近は男の子にも増えています。講演で紹介された意識調査では「グループの仲間同士で固まりたい」「仲間外れにされないように話を合わせる」と答えた男子の割合が増えました。
いつも一緒にいる「いつメン」や、ひとりぼっちだと思われることを恐れる「ぼっち恐怖症」という言葉が象徴するように、子どもたちの人間関係は大きく変わりました。
「東大など有名大学では、ピアサポーターづくりが進められています。大学が仲間づくりをサポートしないと、学生が辞めていく。一匹おおかみは今や絶滅危惧種です」
思春期に見られる自己認識の変化や葛藤、対人関係の変化、感情の不安定さといった心の特徴は「思春期心性」と呼ばれています。思春期の終わりとともに思春期心性も終わりを迎えるかと思いきや、成人後も続くそう。
「常に変化が激しく、先の見えない今の時代と思春期はシンクロする部分があります。思春期心性のない大人はいませんし、これから特徴的になっていきそうです」
24時間オフにならない人間関係…待つ力、1人でいられる力が育まれにくくなっています
こうした思春期心性と相性がいいのがSNSです。
「SNSでは文脈や脈絡を重視せず、瞬間を切り取るコミュニケーションがどんどん増えてきている」と今西さん。「瞬間を切り取る刹那感は、思春期心性によくフィットします」
ネット内での暴言やいじめなどのトラブルは「自分も他者も生身の感覚を失い、デジタルデータになってしまった時に起こりやすい」と言われています。

私たち親世代にはSNSとの距離の取り方に注意を払う意識がありますが、子どもたちは「デジタルネイティブ」「SNSネイティブ」と言われるように、ネットやSNSが生まれた時から当たり前にある世代。友達と実際に会って話すよりも、SNSでのやり取りの方がメインになっているかもしれません。
「待つことができる力や 1 人でいられる力は誰とも交流していない時間に育まれるのですが、今は 1 人でいられる時間がありません。24 時間オフにならない人間関係の中で、SNSですぐに反応があるかどうかで、信頼できるかどうかを測ってしまいがちになっています」
「答えのない事態に耐える力」を備えましょう
思春期は「さなぎの時代」と言われます。成虫に変化する過程のさなぎの中身は、幼虫の体が溶けてクリーム状になっていることから、思春期の激しい不安や混乱に例えられています。
「さなぎの時代」の子どもを育てる親は中年期という「第 2 の思春期」を迎えています。
人の一生を十二支で数えた昔の時刻に当てはめると、思春期は卯の刻、中年期は酉の刻で、ともに昼と夜が移り変わる時間帯になります。酉の刻は夕暮れ時で、魔物に遭遇する「逢魔が時(おうまがとき)」と言われるそうです。

「思春期は『いかに生きるか』を考え、中年期は『いかに死ぬか』を考えます。子どもの抱えている問題と親の抱えている問題が影響し合うこの時期は『逢魔が時』、つまり『危機』なんです」
「危機」と言われると不安が募りますが、「危機は転機になる」と今西さん。冒頭で説明した「子どもとの関わりがうまくいかなくなった時は、自分の捉え方を見つめ直すチャンス」につながりました。

思春期の不安や混乱に加えて、人間関係が複雑になり、先の見通せない社会を生きる今の子どもたちに、私たち親はどう向き合うべきなのでしょうか。今西さんは「ネガティブ・ケイパビリティー」という言葉を最後に紹介しました。
ネガティブ・ケイパビリティーは「不確実なものや未解決のものを受容する能力」などと訳されます。問題解決能力を表す「ポジティブ・ケイパビリティー」と対になる言葉です。
今西さんは精神科医で作家の帚木蓬生さんの著書などから、「答えのない事態に耐える力」「どうしても解決しない時にも持ちこたえていくことができる能力」と説明しました。
物事を理解しようとする時、分かりにくい部分を削っていくと単純化され、分かりやすくなります。ですが、理解は一面的になります。
「私はこの仕事を 30 年やってきましたが、いまだに難しいですし、高校生や大学生と話していると頭を抱えたくなることもあります。子どもが理解できない行動を取った時、大人は理由を知りたがりますが、分かりにくい部分は言葉にしにくいし、無理に言葉にしようとすると誤解される。だから、子どもは『大人は分かってくれないから言わない』となります」
「分かりにくい部分にこそ、その人の核となる部分が含まれているのではないでしょうか。分からない部分を無理に分かろうとしたり、ないものとしたりせず、分からないままに抱えることが時には必要です」
2025年度の研修会日程はこちら
2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」。2026 年 2 月 14 日(土)まで 8 回開かれます。

- 6 月 14 日(土)…幼少期から児童期の子どもの心にそっとタッチ~不安や発達の特性を知って寄り添うコツ~(講師:瀬戸内ナーシング学院学校長・岡田倫代さん)
レポート記事はこちらをタップ▼
「子どもの心に寄り添う」ってどういうこと?「褒める子育て」とは?|乳幼児期~児童期の子育てのこつについて、瀬戸内ナーシング学院学校長の岡田倫代さんが語りました

- 7 月 5 日(土)…思春期と向き合うということ~「子ども理解」から「子どもと大人の関係性への理解」へ~(講師:兵庫教育大学非常勤講師・今西一仁さん)
- 9 月 13 日(土)…子どもの言葉にならない〈ことば〉を聴くために~寄り添う・信じて待つ・かかわり続けるコツ~(講師:はまゆう教育相談所所長・横田隆さん)
レポート記事はこちらをタップ▼
子どもの気持ちが分からなくなった時に取り入れたい「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」|「言葉にならない言葉」を聴くために必要なことは?はまゆう教育相談所の横田隆さんが語りました

- 10 月 11 日(土)…「困った子?困っている子?」育てづらい子どもにかかわる技~子ども理解を通した具体的なかかわりを学ぶ~(講師:高知大学教育学部・是永かな子さん)
- 11 月 15 日(土)…創立 64 周年記念・教育相談研究発表会「子育ては、大人がともに育つこと」ワイワイガヤガヤ子育て談義
- 1 月 17 日(土)…子どもの心を育てる絵本の世界(講師:はまゆう教育相談所部員)
- 2 月 14 日(土)… 1 年間のふり返り・体験発表
この記事の著者

門田朋三
関連記事[子育て]
関連記事[思春期]
-

子どもの不登校、子育てに悩んだ時は?|高知市の「はまゆう教育相談所」に相談できます
-

子どもは思春期、親は中年期…家庭内に訪れる“危機”とは?思春期を迎えるまでにできることは?|兵庫教育大学の今西一仁さんが親子の関わりのヒントを語りました
-

中高生の「親と話したくない」「急にイライラする」「人の目が気になる」は正常です!|思春期を乗り越えるために大人がかけてあげたい言葉とは?東京医療保健大学の渡會睦子さんの授業から考えました
-

子どものうつ、不登校…原因は「甲状腺機能異常」による精神症状かも|思春期にも見られる「甲状腺機能低下症」とは?高知大学医学部の児童青年期精神科、内分泌代謝・腎臓内科で聞きました

 子育て
子育て