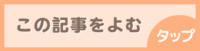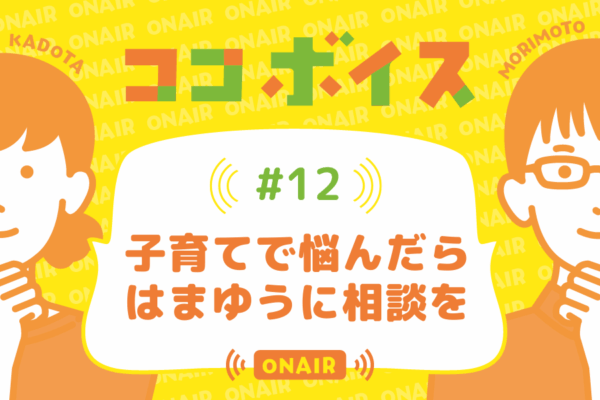「生活習慣が身についていない」「暴れる」「ルールが守れない」…育てづらい子どもへの具体的な関わり方|「困った子」ではなく「困っている子」と理解しませんか?高知大学教授の是永かな子さんが語りました

子どもの発達段階を理解して関われていますか?はまゆう教育相談所の研修会から子育てのヒントをお届けします
生活習慣がなかなか身につかなかったり、感情をコントロールできなかったり、ルールが守れなかったり…お子さんの言動に困っていませんか?
「育てづらい」と感じる子どもへの具体的な関わり方について、「はまゆう教育相談所」の第 5 回研修会で高知大学教授の是永かな子さんが講演しました。
是永さんが呼びかけたのは「『困った子』ではなく、『困っている子』として理解し、その子の気持ちに寄り添ってみませんか?」。子どもへの声かけや伝え方など具体的な関わり方を、困りごとの場面とともに紹介します。
目次
「はまゆう教育相談所」では不登校や子育ての相談に乗っています
「はまゆう教育相談所」は高知市小津町の高知県立塩見記念青少年プラザにあります。小学校の元校長先生らがボランティアで運営していて、無料で相談できます。

活動の一つに「研究」があり、毎年テーマを決めて研修会や教育座談会を企画しています。
2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」で 8 回開かれます。

第 5 回は「『困った子?困っている子?』育てづらい子どもにかかわる技~子ども理解を通した具体的なかかわりを学ぶ~」をテーマに 10 月 11 日に開かれました。
講師は高知大学教育学部の教授・是永かな子さん。研究分野は「特別支援教育」で、スウェーデンなど北欧の教育制度や特別支援教育、特別ニーズ教育の歴史や実態を研究し、県内でも特別支援教育などに携わっています。
「日本ギフテッド・2E学会」の会長も務めていて、先天的に高い知能や得意な才能を持つ「ギフテッド」の人や、ギフテッドと発達障害の特性を併せ持つ「2E(ツー・イー)」の人を支援しています。
【生活習慣が身についていない】すべきことは「直前に」「肯定的に」伝えましょう
基本的な生活習慣を身につけていく上で特に大事なのが 3~6 歳ごろ。是永さんは片付けについて、二つの動画を見せながら説明しました。
散らかった部屋でテレビを見ている子どもを、お母さんが発見した…というよくある場面です。
一つ目の動画のお母さんの反応です。
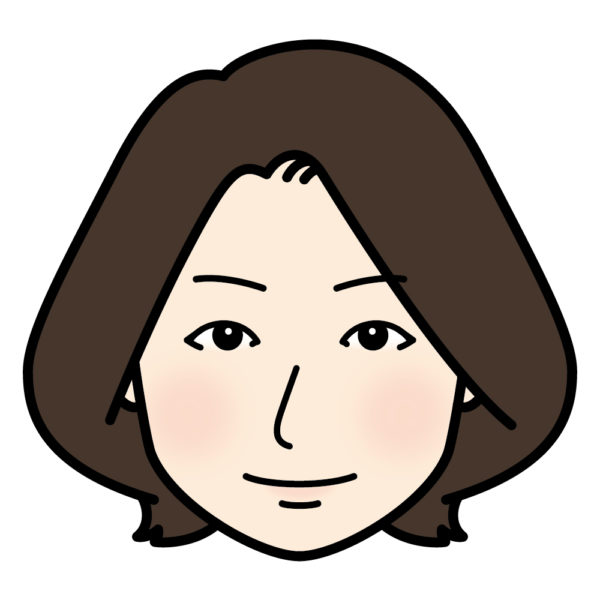
あぁ、言いがち。同じことを何度も繰り返されたらイライラするもの…。
是永さんも「言っちゃいますよね。『何やってんの!』と言われた子どもが『テレビ見てる』と答えると、余計に怒られるとか」と苦笑いでした。
二つ目の動画のお母さんはまずこう呼びかけました。
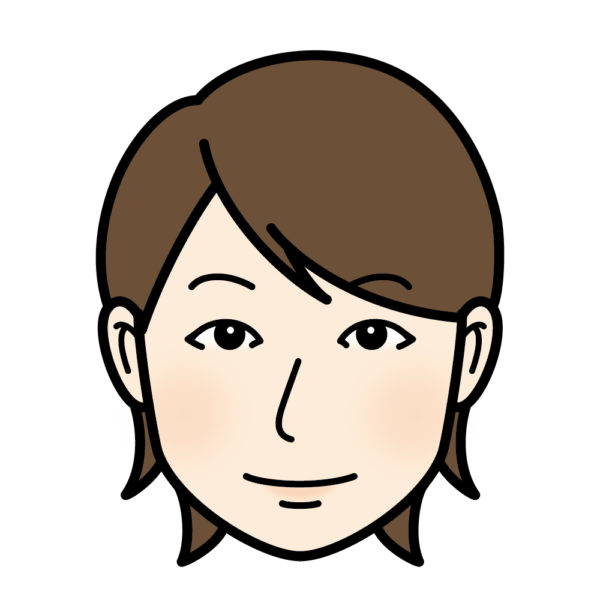
落ち着いたトーンの声でテレビを消すよう促し、「テレビを見る前に片付けようか」と続けました。
「子どもへの上手な伝え方」と聞くと、「頭では分かっているけど、うまくできない…」と思います。是永さんは「子どもに伝わりやすいコミュニケーションとは、自分がイライラしないためでもあるんですよ」と視点を変えてくれました。
「『何やってんの!』という怒りは、相手の怒りを引き出してしまいます。行動を叱責するよりも、『おもちゃを片付けて』とあるべき姿、行動を具体的に伝えましょう」

「生活習慣が身についていない」という困りごとの場合、「そもそも子どもにちゃんと伝わっていない」という理由も考えられるそうです。
伝える際に気をつけたいポイントがこちら。
- テレビや動画など、余計な刺激を取り除く
- 集中しやすい環境をつくる
- すべきことは直前に、肯定形で伝える
- 直前に確認する(本人に言わせる)
- 伝えたいことはゆっくり示す
- やるべきことの量を減らし、スモールステップで少しずつ示す
- 子どもに確認しながら、一緒に進める
例えば、物をよくなくす子どもに対して、「片付ける場所を決める」というのはぱっと思いつく方法。さらに、「子ども自身が管理する物を減らして、残りは親が預かる」「片付ける時間を決める」と工夫を重ねてきます。
「子どもができなければ、親が一緒にやってもOK」とのこと。「忘れ物が多い子は『忘れないように全部持って行く』もあり」と話していました。
【感情のコントロールが難しい】親が先回りせずに、子どもに「どうしたい?」と聞きましょう
「感情のコントロールが難しい」という場面として紹介されたのがこちら。
A君は保育園の年長児。「衝動性が高い」という特性があります。
ある日、保育士さんと一緒に折り紙をしていると、折り紙が扇風機の風で飛びそうになりました。
A君は「あっ!」と不機嫌になりました。様子に気づいた保育士さんは扇風機を消し、A君が怒ることを回避できました。
「これはいい支援と言えるでしょうか」と是永さん。答えは「NO」です。
「怒りを回避できたので一見良さそうですが、A君は『不機嫌になれば大人が対応してくれる』と学んでしまいます。コミュニケーションを学ぶ機会を結果的に奪ってしまうんです」
先回りして回避するのではなく、A君に「扇風機を止める?」と聞きます。「止める」と答えたら、止めましょう。「自分の気持ちやお願いしたことは言葉にしないと伝わらないと教えてください」

同じように「暑い!」とイライラしている子どもには、すぐにエアコンをつけてあげるのではなく、「どうしたい?」と尋ねます。
その上で、「窓を開ける」「エアコンをつける」「服を脱ぐ」などの選択肢を提示し、子どもに決めてもらいましょう。
「理由がないのにイライラしている子どもはいません。何かがうまくいっていないから、不機嫌になります。共感は大事ですが、共感し過ぎると先回りになります。その場ですぐに説得しようとしたり、大きな声で叱りつけたりもせず、子どもを観察して原因を探ってみてください」
【暴れる】言葉の力が弱いことが原因。「暴れるよりもいい方法がある」と伝えましょう
「暴れる」の例がこちら。
Bちゃんは支援センターでおもちゃで遊んでいました。
帰る時間になったので、お母さんが「もうおしまい」と言うと、暴れました。
こちらも幼児期によくある場面。こじれると泣き叫ばれて、周囲の目も気になって、げんなりしますよね。
是永さんによると、こうした子どもの暴言や暴力は「まだ言葉の力が弱く、とっさの一言が出ないから」だそう。この場合も「どうしたいの?」と尋ねます。言葉にできないようなら、「お母さんと遊びたいの?」「ブロックでもっと遊びたかったの?」と原因を探ります。
暴力を止める場合は「何してるの!」と叱るのではなく、「この手を止めます」などと伝えます。

イヤイヤ期を過ぎても、何でも「嫌だ」と返す子どももいます。そんな時は「『嫌だ』だけじゃ、相手には伝わらない」「『嫌だ』と言ってもいいけど、どうしたら嫌じゃなくなるかを考えよう」と促します。
子どもが「もっと遊びたかった」などと言葉で伝えられたら、「言葉で伝わるとステキだね」と褒めましょう。その上で、遊ぶ時間を延ばしたり、一緒に遊んであげるなど、少し折れてあげるといいそうです。

コミュニケーションの取り方を教える際は、「 3 歳児にあいさつの仕方を教える方法」を例に考えてみるといいそうです。四つのステップがあります。
- 意味を短く伝える…「知ってる人に会ったら、『こんにちは』とあいさつしようね」
- 大人が手本を示す…「相手の目を見て『こんにちは』と言うよ」と説明し、実際にやって見せます。
- 子どもにまねさせる…「お母さんのまねをしてやってみよう」と促します。
- 褒める…「それでいいよ」と確認。子どもの自信につながります。
子どもの言動を否定するのではなく、より良い方法を大人が示していくといいそうです。
【ルールを守ることが難しい】しつこく教えるのはNG!短い言葉で伝えましょう
ブランコの順番が守れなかったり、鬼ごっこで鬼にタッチされたのに気にせず逃げ続けたり。ルールを守ることが難しい子どもがいます。場の空気も悪くなり、親としてはいたたまれない場面…。
ルール破りは「ずる」や「わがまま」に見えますが、そもそもルールの意味が分かっていない可能性から考えます。
「話を聞くのは得意だけど、内容を覚えられないという子もいます。ルールは短い言葉で伝え、大人が実際にやって見せましょう」

しつこく教えたり、ルールを破るたびに注意するのはNG。ルールを守らせることにこだわらず、子どもが楽しく過ごせているかを見ていくといいそうです。
子どもと同じ土俵に立たないで…自分をコントロールする方法を知っておきましょう
「怒りは、相手の怒りを引き出す」と語った是永さん。怒りをコントロールする大切さについて、映像も見せてくれました。妹のおもちゃを勝手に触って壊してしまったお姉ちゃんとお父さんのやり取りです。
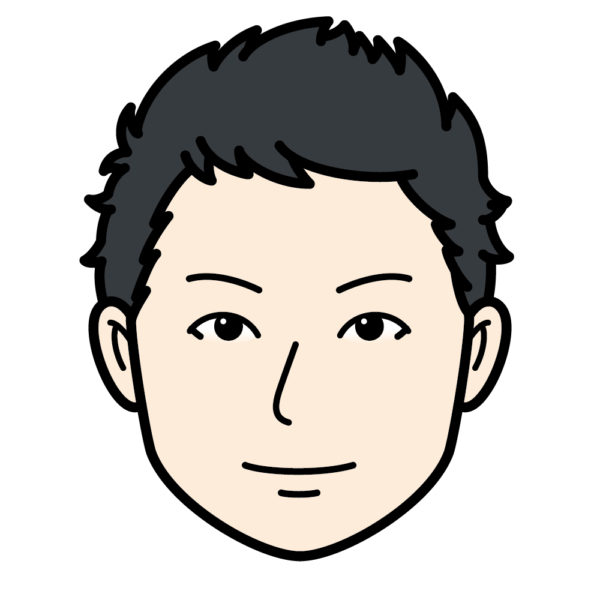
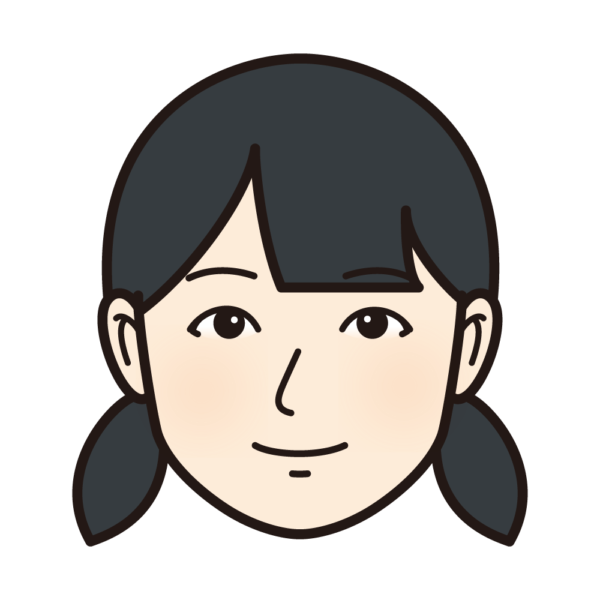
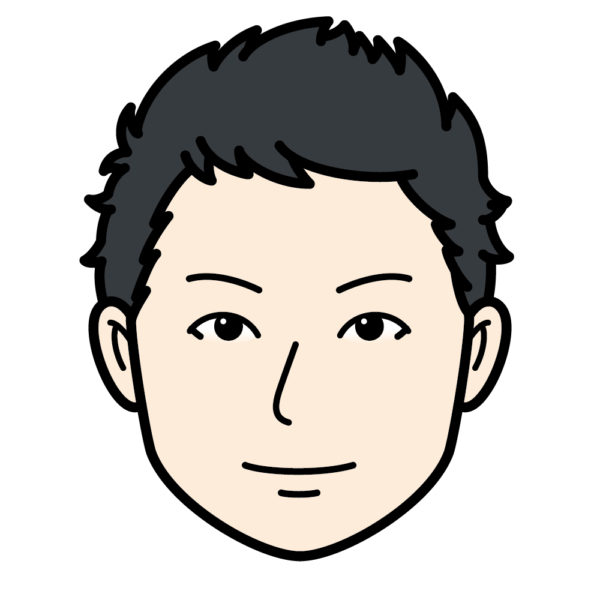
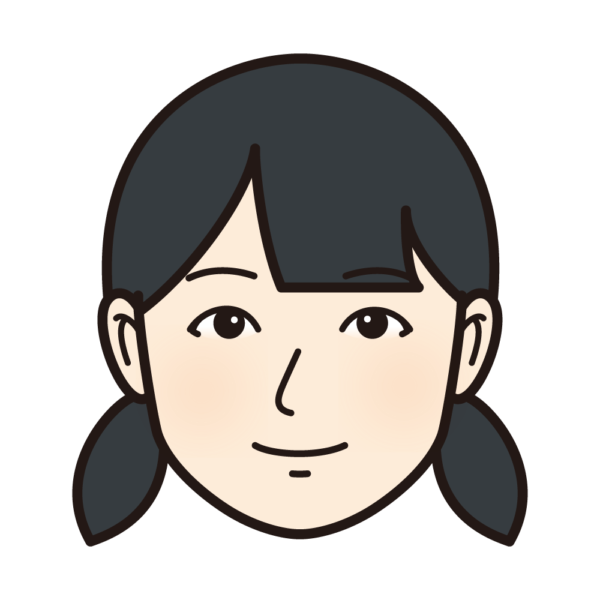
これも身に覚えがあり過ぎるやり取りですが、やはり“火に油”。子どもも親も自分の怒りをコントロールできないまま、エスカレートしていきます。
子どもを落ち着かせようと、親はその場で説得を重ねがちですが、「子どもと同じ土俵に立たないようにしましょう」と是永さん。
「子どもが話をできない状態の時に大人が向き合い続けるのはよくありません。見捨てるのではなく、距離を置く。『1 回、時間を置こう』『お父さん、ちょっと向こうで本を読んでくるね』と離れてください」
親子でぶつかる時に備えて、「自分の部屋に戻る」など、子ども自身が落ち着く方法をあらかじめ一緒に考えておくといいそうです。

距離を置いて落ち着いたら、復活の機会をつくるのは親の役割とのこと。
「『子どもが悪いんだから、子どもが謝るべきだ』と思わず、大人が折れましょう。『子どもになめられたらいかん』なんていい結果を残しませんので、リセットしてくださいね」
講演でも出てきた「何でも『嫌だ』という子ども」。ココハレ編集部員にとっても子育ての困りごとの一つでしたので、「『嫌だ』と言ってもいいけど、どうしたら嫌じゃなくなるかを考えよう」という対応を早速取り入れました。
「どうしたら嫌じゃなくなるかを考えよう」は、視点を他者や過去ではなく、自分や未来に向ける方法だそうです。気持ちの切り替えを親子で上手にしていきたいですね。
2025年度の研修会日程はこちら
2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」。2026 年 2 月 14 日(土)まで 8 回開かれます。

- 6 月 14 日(土)…幼少期から児童期の子どもの心にそっとタッチ~不安や発達の特性を知って寄り添うコツ~(講師:瀬戸内ナーシング学院学校長・岡田倫代さん)
レポート記事はこちらをタップ▼
「子どもの心に寄り添う」ってどういうこと?「褒める子育て」とは?|乳幼児期~児童期の子育てのこつについて、瀬戸内ナーシング学院学校長の岡田倫代さんが語りました

- 7 月 5 日(土)…思春期と向き合うということ~「子ども理解」から「子どもと大人の関係性への理解」へ~(講師:兵庫教育大学非常勤講師・今西一仁さん)
レポート記事はこちらをタップ▼
思春期の子育て…子どもを安易に理解しようとしていませんか?|親が備えておきたい「ネガティブ・ケイパビリティー」とは?兵庫教育大学の今西一仁さんが語りました

- 9 月 13 日(土)…子どもの言葉にならない〈ことば〉を聴くために~寄り添う・信じて待つ・かかわり続けるコツ~(講師:はまゆう教育相談所所長・横田隆さん)
レポート記事はこちらタップ▼
子どもの気持ちが分からなくなった時に取り入れたい「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」|「言葉にならない言葉」を聴くために必要なことは?はまゆう教育相談所の横田隆さんが語りました

- 10 月 11 日(土)…「困った子?困っている子?」育てづらい子どもにかかわる技~子ども理解を通した具体的なかかわりを学ぶ~(講師:高知大学教育学部・是永かな子さん)
- 11 月 15 日(土)…創立 64 周年記念・教育相談研究発表会「子育ては、大人がともに育つこと」ワイワイガヤガヤ子育て談義
- 1 月 17 日(土)…子どもの心を育てる絵本の世界(講師:はまゆう教育相談所部員)
- 2 月 14 日(土)… 1 年間のふり返り・体験発表
この記事の著者


 子育て
子育て