【ココハレインタビュー】助産師・高嶋愛希さん|出産するお母さんを一番に考え、絶対に寄り添う!離島、過疎地…全国でキャリアを積んだ助産師の新しい挑戦

香南市に産後ケア施設「ゆいまーる」を開設。「子育てが楽しい」「また産みたい」を支えていきます
妊娠、出産、そして産後もお世話になる助産師さん。病院やクリニックに勤めたり、地域で家庭訪問をしたり、さまざまな働き方があります。
高嶋愛希さんは高知医療センターでの勤務を皮切りに、都市部や過疎地、離島など、全国各地でキャリアを積んだ、高知県内では珍しい助産師さんです。
現在は宿泊型産後ケア施設の開設に向け、香南市で準備を進めています。
助産師として高嶋さんが大事にしているのが「出産するお母さんを一番に考え、絶対に寄り添う」。「子育てが楽しい」「また産みたい」という気持ちを支えていきたいと、挑戦しています。
目次
一人一人のお産が尊重される社会であってほしい
2024 年 11 月、高嶋さんは高知母性衛生学会の市民公開講座「もっと知りたい『院内助産システム』のこと」に登壇していました。
講座のテーマである「院内助産システム」とは、分娩を扱う医療機関で、助産師が主体となってお産のケアを行う仕組みです。医療の介入の必要のない経膣分娩を対象に、助産師が妊婦健診もお産も担当。リスクが高まった場合や、医療の介入が必要となった場合は、医師主導の健診、お産へと切り替わります。
日本では医師主導の健診、お産が主流。「院内助産システム」はまだまだ珍しく、高知県内では導入に向けて検討を始めた病院が出てきたという段階です。
「産婦人科医不足への対策」という文脈で語られることも多いそうで、この日登壇した産婦人科医は「医師不足を補うためのものではない」「助産師が妊婦さんに寄り添うことで、医療の質を上げ、満足できるお産にしていくことが目的」と強調しました。

高嶋さんは県外の病院での勤務で経験した「院内助産システム」を詳しく紹介。助産師の立場から、語りかけました。
「院内助産システムは助産師が専門性を発揮し、安全性や安心感を確保しながら、その人らしいお産を尊重できる新しいシステムです」
「一人一人のお産が尊重されることが、母子の幸せにつながります。女性が『また産みたい』『また育てたい』と思えるような社会をつくっていきたい」
命の始まりに携わりたいと考え、助産師を選びました
高嶋さんは 1989 年、高知市で生まれました。
母親は助産師で、大学病院に勤務。香南市野市町にある母親の実家で、祖父母と過ごすことの多い幼少期でした。
「家の周りは全部畑!どんな遊びをしても大丈夫でした。おじいちゃん、おばあちゃんとの思い出もあるし、地域のおじちゃん、おばちゃんたちにもかわいがっていただいたし。帰ると、安心できる場所でした」
高校卒業後、看護学校に進みますが、「助産師になろう」とは決めていませんでした。
「命に携わる仕事がしたいと思っていて。命の始まりにいさせていただく助産師も、命の終わりにいさせていただく終末期の看護師も、どちらもすごい仕事。自分はどちらかなぁと考えていました」

進路に迷った時、浮かんだのは幼い頃から見てきた母親の姿でした。
「一緒にスーパーに行くと、知らない方から『出産でお世話になりました』と話しかけられていたし、夜勤もあったのに『仕事が大変』とは一度も聞いたことがなくて。『助産師だ!』とピンときました」
助産師学校に進学し、2014 年に助産師に。高知医療センターで社会人生活をスタートさせました。

高知医療センターは、高知県唯一の「総合周産期母子医療センター」です。高知県内のお産の“最後の砦(とりで)”として、リスクの高い妊婦や新生児を常に受け入れる態勢が整えられています。
仕事は忙しく、「毎日、がむしゃら!産後のケアまで考える余裕は全くなかったです」。
それでも、数々のお産に携わる中で、次第に「助産師として、もっとステップアップしたい」と思うように。2017 年、高知医療センターを辞め、愛媛県の愛媛県立中央病院に移りました。
北海道、沖縄、離島…「応援ナース」で医療過疎の現状を目の当たりに
愛媛県立中央病院は高知医療センターと同じ「総合周産期母子医療センター」で、松山市にあります。お産の件数は当時、年間 1200 件ほど。高知県内の病院よりはるかに多く、リスクの高い妊婦さんにも対応していました。
職場を変えたことは、高嶋さんに変化をもたらしました。
「新しい学びにもなるし、固定概念が一つ一つ取り払われるのが分かりました。経済的な困窮などのリスクを抱える妊産婦さんへの対応では、地域との連携も勉強になりました」
ですが、頑張れば頑張るほど、「タスクに追われている」と感じるようになります。
「双子や三つ子の妊娠、病気、切迫早産などで長期入院の方がいましたが、忙しくてゆっくり話が聞けないんですね。私がベテランだったら、もっとうまくやれたと思いますが…」
「自分に余裕がないと、人を幸せにできない」と考えた高嶋さん。働き方を変えるため、次に選んだのが「応援ナース」でした。

「応援ナース」は「トラベルナース」とも呼ばれます。人手が不足している医療機関などで一時的に働く看護師のことで、雇用期間は原則 6 カ月。働く場所は「都市圏」「北海道」「沖縄」「離島」から選べます。
高嶋さんは沖縄の病院を皮切りに、京都、北海道と職場を変えました。
医療機関側で即戦力として期待されるのが「応援ナース」。新しい環境に短期間でなじんでいかなければなりません。
「助産師のキャリアは上でも、新しい職場では新人。常にフレッシュな気持ちで臨みました。年下の同僚にも教えてもらうし、助けてもらう。その病院、その地域、その県によってやり方や文化が違うということも学びました」

それぞれの地域の医療課題にも直面しました。
北海道の病院はオホーツク海に面した過疎地域にありました。お産の件数は少なく、月に 1、2 件ほど。妊娠中から「顔の見える助産師」として妊婦さんにゆっくり寄り添えましたが、緊急時は一変しました。
「搬送先までは救急車で 2 時間かかります。私が働いていた時、34 週で生まれた赤ちゃんがいて、救急搬送となりました。酸素投与が必要で、私が 2 時間、手動でやることになりました。新生児用の小さな蘇生バックを押して空気を送りながら、『私が手を止めたら、この赤ちゃんは死んじゃうんだ』と怖かったです」
離島でも過疎の現状を目の当たりにしました。奄美大島では 2 カ所あった分娩施設が 1 カ所に減りました。
「周辺の離島から奄美の病院に通う妊婦さんもいます。病院がなくなったら、地域でお産できなくなるということ。医療の集約化の必要性は分かりますが、そこで暮らしている人のことを考えると、安易に言ってはいけないと強く感じました」
助産師主導の産院「音々」で生まれた、助産師としての信念
全国各地で働く間には、新型コロナウイスル感染症の流行もありました。高嶋さんは高知に戻り、クリニックで働きながら、オンラインで勉強を続け、チャンスがあればまた県外で働きました。
その一つが、長野県御代田町にある産院「音々(ねね)」。軽井沢西部総合病院の敷地内にあり、スタッフは医師 1 人と助産師 15 人。助産師主導で妊婦健診、分娩、産後ケアを担当しています。
助産師は施設勤務ではなく、業務委託されています。お産ごとに担当が決まり、報酬も病院からの給与ではなく、そのお産ごとに支払われるという珍しいシステム。分娩施設の閉鎖が全国で相次ぐ中で注目されています。

助産師である自分が主体となり、担当する妊婦さんに長く関わっていく。出産を前にじっくり話し合い、どんなお産がしたいかを自己決定してもらい、希望をかなえていく――。
「音々」での経験は、高嶋さんの助産師人生に大きな影響を与えました。
「『助産』とは何だろうと、すごく考えました。お産って本来は自由なものだし、どこで産むか、どんなふうに産むかを決める権利は女性にある。その人が望むお産を安心してできるように、安全にガイドするのが助産師の役目なんだなと」
「健診から産後ケアまで同じ助産師さんで、安心できた」「高嶋さんに出会えてよかった」。退院するお母さんたちからそんな声をかけてもらい、芽生えたのは「産むお母さんを一番に考え、絶対に寄り添う」という信念です。
「自分の信念がぶれなければ、どこで働いても、どんなやり方でも、幸せなお産、よりよいお産を実現できると思うようになりました」
「また産みたい」を香南市から広げていきたい
高知、愛媛、沖縄、京都、北海道、長野、鹿児島の計 10 施設でキャリアを積んできた高嶋さん。活動拠点を高知に移すため、2021 年には訪問型助産院「ゆいま~る」を開設。現在は宿泊型産後ケア施設の開設に向けて、準備を進めています。
選んだ場所は、香南市の祖父母の自宅。高嶋さん自身にとって「安心できる場所」です。
「わが家は母と姉と私が助産師で、妹が保健師なんです。『家族みんなで子育て支援ができたらいいね』と以前から話していて、実現させるなら今のタイミングだと考えました」

高知県内でも分娩施設は減り続けています。県東部では安芸市の県立あき総合病院のみ。産後ケア施設も高知市内に集中しています。産後は入院期間の短縮が進み、子育てに不安を抱えながら退院するお母さんたちがいます。
高嶋さんも「実家が遠くて頼れる人がいない」「誰にも相談できずに追い詰められる」「SNSの情報が多過ぎて、何が正しいのか分からない」というお母さんたちの声を受け止めてきました。
「『また産みたい』と思えるのって、いいお産はもちろんですが、出産後に安心できる場所、支えてくれる場所があってこそですよね。『ゆいま~る』を拠点に、『ここで子育てできてよかった』と思ってもらえる地域を、香南市から広げていきたいんです」

しばらくは宿泊型施設の運営に専念しますが、心に常にあるのは「出産するお母さんを一番に考えたい」という信念です。
「赤ちゃんを産むことは、本来は特別なことではなく、自然な営みの一つです。分娩施設が減る中で、女性が自分の生き方として産む場所を選べるように選択肢を守っていくのも、助産師の大事な使命ではないでしょうか」

助産師として歩み、12 年。さまざまな医療施設で働いてきた経験を高知で生かし、県外のいいシステムは取り入れていきたいと考えています。
「助産師は女性の一生に関われる仕事。今よりもっと活躍できるし、後輩たちには仕事のやりがいを伝えていきたい」。高嶋さんはキラキラした目で最後にこう語りました。
「高知の周産期医療は大変な状況ですが、幸せなお産は地域の未来を変える力になると信じています。今しかできないことに全力で取り組んで、仲間を増やし、大変な状況を幸せな方向に変えていきます」
「ゆいま~る」では宿泊型産後ケア施設の開設に向け、施設に必要な防災設備や備品の購入費用などを募るクラウドファンディングに挑戦しています。目標額は 250 万円で、3 月 31 日まで。
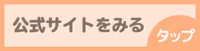
この記事の著者


 子育て
子育て







