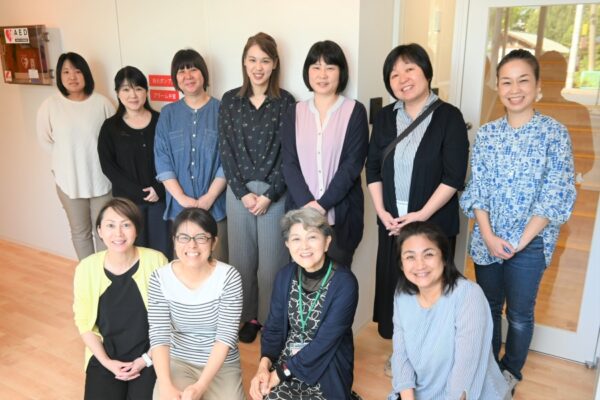「子どもをこう育てたい」ではなく、子どもが必要としていることを考え、満たしてあげて|里親家庭から考える子育てとは?青山学院大学教授の横堀昌子さんが語りました

さまざまな事情で家族と一緒に暮らせない子どもたちを家庭に迎え入れて養育する「里親制度」。里親の役割や里親家庭で暮らす子どもたちの思いを知ってもらおうと、里親支援センター「結いの実」では毎年、講演会を開いています。
2025 年の講演会には、青山学院大学教授の横堀昌子さんが登壇しました。
横堀さんは両親が運営するファミリー・グループホームで、里親委託された子どもたちと暮らしてきました。
講演会では子どもたちとの関わりを紹介しながら、「『子どもをこう育てたい』ではなく、子どもが何を必要としているのかを考えて、ニーズを満たしてあげてほしい」と呼びかけました。子育てで大事にしていきたいメッセージを紹介します。
目次
横堀昌子さんの講演会は、里親支援センター「結いの実」(高知市新本町 1 丁目)が主催。「里親家庭というもうひとつのおうち~里親家庭の実子として暮らした日々を通じて~」と題し、2025 年 9 月 27 日に高知市追手筋 2 丁目の高知城歴史博物館で開かれました。
「家族」って何だろう…里親家庭で実子として暮らしながら考えました
横堀さんは青山学院大学コミュニティ人間科学部の教授。「社会的養護」「ソーシャルワーク」が専門で、里親制度やフォスタリング(里親養育包括支援)に関わる専門職の育成などにも取り組んでいます。
出身は群馬県。両親は児童養護施設の職員で、自宅は施設内にありました。横堀さんは「小さい頃から、施設で暮らすお兄さん、お姉さんが取り合いっこのように私と遊んでくれた」と振り返りました。
横堀さんが中学生だった 1982 年、両親は社会的養護が必要な子どものために、ファミリー・グループホーム「横堀ホーム」を開設しました。当時は子どものためのグループホームの制度がまだなかったため、両親は私財を投じて小規模な家庭養育を目指しました。

横堀ホームで子どもを受け入れるため、両親は里親登録をします。施設への入所が難しい子どもの委託に加え、行政などから特別に依頼があり、ホームでの生活を必要とした大人も受け入れてきました。
虐待された経験のある子ども、非行や不登校の状況にある子ども、障害のある子どもや大人、ホームレスだった人、若年性の認知症の人、身寄りのない高齢者…。
彼らと生活を共にする中で、横堀さんは「家族って何だろう」「どこからどこまでが家族?」と考えてきました。
「上野千鶴子さんが提唱した『ファミリー・アイデンティティー』、それは多様です。血のつながりや、同居しているかどうかではなく、あなたが家族と思う人が家族でいい。大学の授業でこう話すと、ほっとした顔をする学生がいます」
両親が受け入れてくれた甘え…大きなエネルギー源になりました
生まれた時から「社会的養護」が身近にあった横堀さん。講演では小学 3 年生の時の思い出を語りました。
「夜はいつも両親が施設の子どもたちのお世話でいないんですが、その夜は母親がいました。私は思いきり甘えたくなって、お風呂で『洗えない』と伝えました」
母親は「小学 3 年生だから自分で洗いなさい」とは言わず、「そうなんだ。分かった」と全部洗ってくれました。
「遠出をして車で寝てしまうと、父がお姫様抱っこをして車から降ろしてくれるんです。お姫様抱っこをしてほしくて、寝たふりもしました。両親が私の甘えに応えてくれたことは、後々、大きなエネルギー源になりました」

成人し、結婚もした横堀さん。多くの子どもとの育ち合いはかけがえのないものでしたが、子どもの頃からずっと、自分の誕生日を当日に祝ってもらえなかったことが心にしこりのように存在していました。
ある年、誕生日当日に実家に帰ります。
「うらみがましく生きるんじゃなくて、『お祝いして』と頼んでお祝いしてもらって、溶けるものがありました。大人になってからの自己決着であり、支えになりました」
自身の経験も含め、子どものニーズに応える大人の存在の大切さを実感したそうです。
この子は今、何を必要としている?大人の思いよりも子どもを優先
講演会では、「子どもの権利」について、児童福祉の専門家・許斐有(このみ・ゆう)さんの言葉を紹介しました。
「子どもの権利とは、自分が大事にされていることを、子ども自身が実感できることである」
この言葉を、横堀さんは「家庭での生活そのもの」と捉えています。
「夏、子どもが帰ってきたら、『暑かったね』『アイスあるよ』『お茶もあるよ』『どのコップで飲む?』と声をかけますよね。子どもに『待ってたよ』『あなたがここに来てくれてよかった』と言葉で伝えるのが生活の中にある福祉。『どんな子どもも、大切な子ども』と伝えるのが子どもの権利保障です」

横堀さんは明治学院大学大学院を卒業後、東京の児童養護施設で小規模ケアに従事。横堀ホームで両親とも働きました。
ホームで子どもを受け入れる際は、子どもの「不安」や「不快」を受け止め、ニーズに添って対応していくそうです。
例えば、「○○ちゃんの好きな物を作ったよ。一緒に食べよう」という言葉で、寂しかった食事が楽しい時間に変わります。「不快」を「快」に変えてもらうことで、子どもはニーズをより表現できるようになります。
「『おい、おやつにチョコレート出せよ!』なんて乱暴に言う子は、『俺の好きな物を知ってるんだろ?対応してくれよ』と言っています。子どもをがでこぼこを見せてくれるのは、回復に向かった証しなんです」
「『子どもをこう育てたい』という大人の思いよりも子どもが先。子どもが必要としていることを満たしてあげてください」
ニーズを満たすことが幸福感、満足感につながり、安心や信頼につながります。ポジティブな相互作用の中で自尊感情や愛着が育まれていきます。
「○○ちゃんの時間」「王子様・お姫様ごっこ」…大人から大切にされた経験を
ホームで暮らす子どもたちの中には、大人を困らせるような行動を取る子どももいました。
横堀さんは「人を裁かずに受け止め、生活や関わりを楽しむこと」を大切にしてきました。
「『良くないことをしたから、クリスマスプレゼントはなし』などではなく、『いろんなことがあるからこそ、ご飯は一緒に温かく食べよう』ですね」
グループホームという家庭での養育ならではのケアも紹介されました。
「手がかかる子ばかり相手をしていると、そうでない子への関わりが減ります。『今は○○ちゃんの時間』と決めて個別に関わったり、その子のいいところを歌詞にした『○○くんの歌』を歌ったりしました。『やめろよ~』と言いながら、にこにこしていましたね」

寝る前の「王子様・お姫様ごっこ」も子どもたちに大人気でした。
「私が家来になって、『王子様、お布団を掛けてさしあげます』。ふわっと掛けて、優しくとんとんします。『ウルトラマンを持ってこい』と命令されたら、持っていきます。柔らかい笑顔を見せ、よく寝ました」
「魔法のおにぎり」は、ごく小さなおにぎりと小さなカップ入り麦茶の特別セットです。
虐待された経験のある子どもの中には、食が落ち着かない子どもがいました。どんなにたくさん食べても心が満たされず、自分から「ごちそうさま」が言えなかったそうです。
横堀さんは「おなかがいっぱいになる魔法のおにぎりなんだけど、食べたい?」と伝え、子どもに決めてもらいました。食べる時は子どもを膝に乗せ、ぎゅっと抱っこしました。食べ終わった後、しばらく「どうかな?」と寄り添っておなかをなでていると、子どもは「あ、だんだんいっぱいになってきた。こちそうさまー」。他の子も食べたがり、よく作ったそうです。
これらは子どもにとって、心が満たされた経験、大人から大切にされた経験となりました。
「子どもは体験することでしか、この世界を理解できません。特に被虐待経験を持つ子どもは、自分を虐待しない大人との出会いに意味があります」
横堀さんは「子どもは出会う体験を栄養にして、自分を生き始める」とも。大人から大切にされた経験が、自分や誰かを大切にしていくことにつながるそうです。
「子どもをどう育てるか」ではなく、「私たちがどう生きていくか」
講演では、横堀さんがこれまで関わってきた子どもたちの言葉も紹介されました。
万引を繰り返す子どもがいました。警察から連絡があるたびに、横堀さんは迎えに行きました。夕日が照らす帰り道、横堀さんは一緒に歩きながら、「もしかして、この子はこの時間が欲しいのでは」と気づきました。
「あなたの行動は間違ってる。あなたの信用が落ちる行動で、もったいない」。一通り必要なことを話した後、「ちゃんと話したから、もうおしまい。明日からのあなたを信じてる」と伝えると、子どもは号泣しました。
「こんなにも迷惑をかけてる俺のことを、それでも信じるって言ってくれるの?」
この子にとって、大人から見放されなかった経験となりました。

子育てに関して、最後に作家・渡辺一枝さんの言葉が紹介されました。
「子どもをどう育てるかではなく、私たちがどう生きていくかが、子どもを育てていくのです」
社会的養護を必要とする子どもたちとの関わりや、里親家庭で実子として育った横堀さんの思いを聞き、「子どもにとっての幸せとは何か」をあらためて考えさせられました。子どもの頃、ちょっとした甘えを受け入れてもらえた経験が大人になってからのエネルギー源となるというお話は、自分自身にも当てはまりました。
親となった今、わが子にエネルギーをチャージできているだろうか…とも考えました。「忙しい」を理由にせず、時々はのんびり、子どもに向き合ってみたいと思います。
この記事の著者


 子育て
子育て