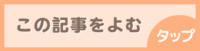不安、怒り、憎しみ、悲しみ…ネガティブな感情に向き合えていますか?|子どもの感情を育てるには?はまゆう教育相談所の研修会にココハレサポーターズが登場しました

子どもに「クソババア」と言われたら子育ては成功?!はまゆうの研修会から子育てのヒントをお届けします
不安や怒り、憎しみ、悲しみ…。ネガティブな感情は表に出したくないし、できれば見たくない、触れたくないもの。でも、子どもの成長過程ではこういった「不快感情」を安心して大人に出し、受け止めてもらう経験が必要なのだそうです。
不登校や子育ての相談に乗る「はまゆう教育相談所」の第 1 回研修会が開かれ、子どもの感情を育てることについて考えました。ココハレサポーターズから 3 人のお母さんが登壇し、“令和の子育て事情”を語りました。
研修会は「子どもに『クソババア』と言われたら子育て大成功って本当?」という何とも刺激的なタイトル。詳しく紹介します。
目次
「はまゆう教育相談所」では不登校や子育ての相談に乗っています
「はまゆう教育相談所」は高知市小津町の高知県立塩見記念青少年プラザにあります。小学校の元校長先生らがボランティアで運営していて、無料で相談できます。

活動の一つに「研究」があり、毎年テーマを決めて研修会や教育座談会を企画しています。
2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」で 8 回開かれます。


「育児」と一緒に検索されるワードは?「疲れた」「イライラ」…
研修会ではまず、横田さんが「『育児』と聞いてどんな言葉を思い浮かべますか?」と質問しました。
横田さんによると、インターネットで「育児」とともに検索されるワードがこちら。
- 第 1 位…疲れた
- 第 2 位…イライラ
- 第 3 位…イライラが止まらない、だんなにイライラ
では、どんな時にイライラする?横田さんが県内の保育園でお母さんたちと話してきた中で多かったのがこちら。
- 子どもが親の言うことを聞かない
- 子どもに落ち着きがない
- 家庭でのルールづくりが難しい
- 大人中心の生活リズムを変えることが難しい
- 食事に対する興味、意欲が低い
- 子育てをYouTubeやアプリに頼ってしまう
毎日頑張っているのに、子どもに丁寧に向き合いたいのに、うまくできない…という姿が浮かびます。
横田さんはたくさんの保護者と接してきた中で、「完璧な子育て」を目指す危うさを感じています。
「『子どもは親や先生の言うことを聞くものだ』と思っていると、子どもが思い通りにならないとイライラします。『普通は』『みんなは』『当たり前』にとらわれて、自分の子どもと他の子どもを比較して落ち込んだり、苦しんでいたりという親御さんもいます」

現代は「子どもの感情が育ちにくい環境になっている」と考えています。
「少子高齢化の波で、地域の町内会や団体では担い手がいなくなってきました。つまり、家庭をサポートする地域コミュニティーが崩壊の危機にあります。学校や園は期待される役割と責任が大きくなり、先生が多忙化しています」
子どもの周囲にいる大人が「家庭」や「学校・園」に限られると、人間関係は固定化されます。
「子どもはたくさんの大人と関わり、言葉のシャワーを浴びながら自尊感情を育みます。人間関係が固定化されると、コミュニケーション能力も育ちません」
地域の在り方が変わり、子どもも親も孤立し、生きづらさを感じている。そんな構図が考えられるそうです。
“イライラ虫”はどうやって収める?「ラジオを聞く」「ノートに書く」「口に出す」
ここで、サポーターズの 3 人が登壇。「どんな時にイライラする?」「イライラ虫をどうやって収めてる?」との質問に答えました。
松本容子さんは「段取りを崩されるとイライラする」そう。「今朝も 9:00 に出かける予定なのに、ご飯をまき散らされて、ご飯粒を拾っていたら遅くなって、イライラしました(笑)」
物事を段取りよく進めるには、無駄を省く必要があります。でも、この「無駄」は大人の視点。「一見すると無駄なことから子どもは学んでいると分かってはいるんですが…」と話していました。

上野萌栞さんは、子どもが言うことを聞いてくれないことがイライラポイント。好奇心旺盛な 2 歳の長女が先日、キッチンのグリルを触ってしまったそう。
「『危ないから触らないで』って何度も伝えてるのに、目を離した隙に触ってしまいました。『危険なのにどうして聞いてくれないの?』と思うし、『私が目を離したからだ』というふうに自分の責任だと捉えることにも疲れます」

谷江さんは「自分のやりたいことをやりたい時にできない」ということに疲れています。「公園に行くと、心が疲れる」そう。
「公園で子どもを遊ばせていると、『母親としてやるべきことをやっているけれど、私がやりたいことじゃない』と思っちゃいます」
4 歳の長男にはまだまだ手がかかります。
「『ママ、遊んで!』で全ての家事がストップします。家事をしたかったら、YouTubeを見せるしかないのもストレスですね」

そんな 3 人の「イライラ虫の収め方」がこちら。


うれしかったこと、悲しかったことをノートに書きます。自分の心が動いたことを読み返すと自分がイライラするパターンが分かるので、対応を考えています。

イライラ虫の収め方は三者三様。「その場から離れる」「口に出す」など方法は違いますが、「イライラする」というネガティブな感情を押し込めたり、ネガティブな感情を抱いた自分を否定しないという点が共通しているようでした。
「子どもの感情を育てる」とは?感情を言語化していきます
「『子どもの感情を育てる』ってどういうこと?」ということで、横田さんが再び登壇しました。

会場からは「うれしいね」「楽しいね」「気持ちいいね」などが挙がりました。大人が子どもに言葉をかけることで、子どもに湧き上がっている感情と言葉がつながります。これを「感情の社会化」と言うそうです。
続いての質問がこちら。

転んで痛がっている子どもへの「痛かったねぇ」という声かけは、「感情の社会化」です。一方で、「痛くない!」「男の子なら泣かない!」などの声かけは、「感情の抑圧」につながります。
「『痛くない』とか、我慢して立ち上がった子に『偉い!』とか。大人からの声かけに悪気があるわけではないですが、抑圧がずっと積み重なるとどうなるでしょうか」

ネガティブな感情には不安、怒り、憎しみ、恐怖、悲しみ、寂しさなどがあります。
横田さんによると、大人は「子どものネガティブな感情は見たくない」と考えがち。理由は「大人が嫌な思いをしたくないから」だそうです。さらに、「いつもにこにこして、素直で元気なポジティブな子どもが思いやりのある大人に育つ」という誤解もあるそうです。
「ネガティブな感情を見たくない」という大人からのメッセージを子どもは敏感に受け止め、「ネガティブな感情は出してはいけない」と学びます。
「子どもは周囲の大人の思いや期待に添うように頑張りますから。ポジティブな感情とネガティブな感情を行ったり来たりするのが健康なのですが」
ネガティブな感情を我慢し続けると、大人にとっての「いい子」でいようと頑張る「過剰反応」となったり、逆に周囲に対して攻撃性が高まったりと、思春期以降に問題が現れるそうです。
子どもの感情の育て方や感情の社会化については、臨床心理士の大河原美以さんの書籍「怒りをコントロールできない子への理解と援助 教師と親のかかわり」(金子書房)、「ちゃんと泣ける子に育てよう―親には子どもの感情を育てる義務がある」(河出書房新社)で紹介されています。
「クソババア」は親の力を乗り越えようとし始めた証しです
子どもが転んで痛がっている時に「痛かったねぇ」と感情を言語化していくことは、子どもにとって「『痛い』という感情を安心して出していい」というメッセージにもなります。
「『ネガティブな感情や不快な感情を安心して出していいんだ』と大人から学ぶと、そういった感情を安心して抱えられる子どもが育つと言われます」
感情を育てる指標の一つとして、「ちゃんと泣ける子に育てる」があるそうです。

ここで横田さんが紹介したのが「子どもにクソババァと言われたら 思春期の子育て羅針盤」(教育出版)という本。著者は田村節子さん、高野優さんです。
「クソババア」とはいい言葉ではありません。何ともネガティブで、我が子から言われると傷つきます。ですが、「子どもが成長し、親の力を乗り越えて自立しようと歩み始めた証し」と捉えると、見方が変わります。
「『ヘリコプターペアレント』『カーリングペアレント』と呼ばれていますが、子どもが困った時に親が何でもすぐに助けたり、親の思う通り真っすぐ歩ませるために道を磨き続けたりしていると、子どもは自分で動いたり、解決したりできなくなります」
きっかけは「クソババア」だけではありませんが、最初は「ヘルプ」だった子どもへの関わりを徐々に「サポート」に変えていくことが大事。子どもをサポートしていくためには、親自身にもネガティブな感情を安心して抱える力が必要だそうです。
子育てへの不安…できない自分を認めて、楽観的に!
研修会では、子育て中の親が漠然と抱える不安を上野さん、谷江さんが打ち明けました。


2 人は子育てでプレッシャーを感じないように、「私以外の大人も我が子に関わってくれている」「私がダメな親だったとしても、反面教師として子どもが成長してくれるはず」と楽観的に考えるようにしています。
3 人を育てる松本さんはこんな話をしました。

「自立」という言葉には「他の人の力を借りず、自分で」という意味が含まれますが、横田さんは「自立するとは依存することです」と呼びかけました。
子どもの感情を育てていくには、まず親自身が自分一人で頑張り過ぎない、「完璧な子育て」を目指さないことが大事だと学んだ研修会でした。
2025年度の研修会日程はこちら
2025 年度のテーマは「子どもの笑顔を育むために、私たち大人は?」。2026 年 2 月 14 日(土)まで 8 回開かれます。
- 5 月 10 日(土)…子どもにクソババアと言われたら、子育て大成功って、本当?~令和のお母さんに学ぶ子育て事情~
- 6 月 14 日(土)…幼少期から児童期の子どもの心にそっとタッチ~不安や発達の特性を知って寄り添うコツ~(講師:瀬戸内ナーシング学院学校長・岡田倫代さん)
レポート記事はこちらをタップ▼
「子どもの心に寄り添う」ってどういうこと?「褒める子育て」とは?|乳幼児期~児童期の子育てのこつについて、瀬戸内ナーシング学院学校長の岡田倫代さんが語りました

- 7 月 5 日(土)…思春期と向き合うということ~「子ども理解」から「子どもと大人の関係性への理解」へ~(講師:兵庫教育大学非常勤講師・今西一仁さん)
レポート記事はこちらをタップ▼
思春期の子育て…子どもを安易に理解しようとしていませんか?|親が備えておきたい「ネガティブ・ケイパビリティー」とは?兵庫教育大学の今西一仁さんが語りました

- 9 月 13 日(土)…子どもの言葉にならない〈ことば〉を聴くために~寄り添う・信じて待つ・かかわり続けるコツ~(講師:はまゆう教育相談所所長・横田隆さん)
レポート記事はこちらをタップ▼
子どもの気持ちが分からなくなった時に取り入れたい「どうしたの?」「どうしたいの?」「何をしてほしいの?」|「言葉にならない言葉」を聴くために必要なことは?はまゆう教育相談所の横田隆さんが語りました

- 10 月 11 日(土)…「困った子?困っている子?」育てづらい子どもにかかわる技~子ども理解を通した具体的なかかわりを学ぶ~(講師:高知大学教育学部・是永かな子さん)
- 11 月 15 日(土)…創立 64 周年記念・教育相談研究発表会「子育ては、大人がともに育つこと」ワイワイガヤガヤ子育て談義
- 1 月 17 日(土)…子どもの心を育てる絵本の世界(講師:はまゆう教育相談所部員)
- 2 月 14 日(土)… 1 年間のふり返り・体験発表
この記事の著者


 子育て
子育て